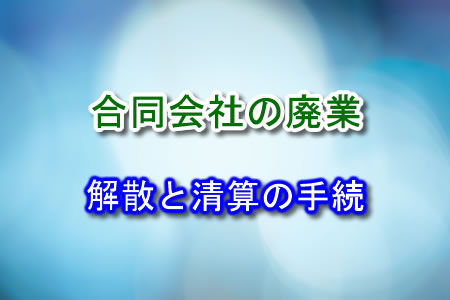
業績不振や後継者の不在など、何らかの理由で事業活動を継続する事が出来なくなることがあります。
そんな時の選択肢の1つが、「解散」です。
法的に会社を消滅させるには、「会社の解散」→「清算手続き」→「清算結了」の流れで手続きが必要です。
会社の設立は、書類を作成して届け出を行うだけで簡単でしたが、法人を消滅させるには抹消登記の前に事務処理がいろいろあり、手間と時間を要します。
このページでは、合同会社の解散と清算の手続きについての概要を解説します。
廃業の大まかな流れと処理の概要
合同会社を廃業する時の大まかな流れについて解説します。
まず最初に「解散」の手続きを行い、清算人を選定します。
続いて「清算」の手続きに入ります。
「清算」の段階では、清算人は概ね次の順で処理を行います。
- 解散および清算人の登記
- 税務官庁へ、会社解散届の提出
- 解散日の財産目録・貸借対照表の作成
- 債権申出の公告および債権者への通知
- 税務官庁へ、解散事業年度の確定申告書の提出
- 債権取立・債務弁済・財産換価
- 税務官庁へ清算事業年度の確定申告書の提出
- 残余財産の確定及び分配
- 税務官庁へ、残余財産確定事業年度の確定申告書の提出
- 清算結了登記
- 税務官庁へ、清算結了届の提出
解散時の登記登録免許税は39,000円。
清算結了時の登記登録免許税は、本店のみの場合は2,000円。
支店がある場合は登録免許税2,000円×本店と支店の合計数と、登記手数料300×支店数が必要です。
「解散」の手続きとは?
合同会社を廃業するには、まず最初に会社法471条~に該当する、会社の法人格を消滅させる法律的事実がなければ、手続きが始まりません。
解散には大まかに分けて、任意解散と強制解散があります。
解散の種類
任意解散
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散事由の発生
- 総社員の同意
- 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
強制解散
- 破産手続開始の決定
- 解散を命ずる裁判(解散命令または解散判決)
- 休眠会社のみなし解散
会社の解散は、その原因によって法律の適用関係や手続きに違いが出てきます。
会社が解散すると、清算手続(破産の場合は破産手続)が開始されます。
このサイトでは、総社員の同意による解散を前提に解説します。
合同会社の場合は、総社員の同意(社員が1人ならば社長本人だけ)があればいつでも解散することができます。(株式会社の場合は、株主総会の決議により解散します)
清算人の選任
総社員の同意による解散の場合は、解散前の合同会社で業務を執行していた社員(社員が1人ならば社長)が清算人になるのが原則です。
例外的に、定款で別段の定めがあり清算人が定められているか、業務執行社員の過半数の同意によって選任することもできます。(会社法647条1項)
解散後は、営業活動ができない
解散した後は、会社の財産を整理する範囲内でのみ存続することになるので、営業活動はできなくなります。
売掛金等の回収や、棚卸資産として残っていた在庫を売却処分により換価するのは良いですが、利益を目的として新たに生産したり仕入れるなどして売却することはできません。
「清算」の手続きとは?
総社員の同意による「解散」の手続きが済んだら、次は「清算」の手続きに入ります。
「清算」は、会社を取り巻く法律的・経済的関係を処理し、法人格を消滅させるために実行される手続きをいいます。
具体的には、次の一連の清算業務の結了によって、会社の法人格が消滅します。
- 現務の結了
- 債権の取立て
- 財産の換価処分
- 債務の弁済及び残余財産の分配
清算の種類
清算には、法定清算と任意清算があります。
「法定清算」は、法律上定められた手続きによって財産の整理を進めていく方法で、株式会社はこの方法で行わなければいけません。
「任意清算」は、定款の定めや総社員の同意によって会社財産を自由に処分できる方法で、持分会社である合同会社・合名会社・合資会社にのみ適用が認められています。
このサイトでは、任意清算を前提に解説します。
清算人の作業内容
清算人は、次の①~⑪までの作業のほか、雇用保険や社会保険の適用を受けていれば、その手続も必要です。また、金融機関等の解約手続きや、事務所などを借りていれば賃借物の解約などの作業もあります。
①解散および清算人の登記
清算人は、解散の日から2週間以内に、次の事項に関する登記を行わなければいけません。
- 清算人の氏名または名称および住所
- 清算合同会社を代表する清算人の氏名または名称(清算合同会社を代表しない清算人があるばあいに限る)
- 清算合同会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名および住所
[詳細記事]合同会社の廃業(解散)時に必要な書類と「登記申請書」の作り方
②「会社解散届」の提出
解散日後、解散の登記が完了してから遅滞なく、税務署・都道府県税事務所・市区町村へ「会社解散届」を提出します。
届出書の正式名称は、「異動届出書」です。
税務署への提出分の用紙は、国税庁のサイト 異動事項に関する届出 からPDF版の「異動届出書」を入手することができます。
都道府県および市区町村の用紙についても、各自治体のページからダウンロードで入手できます。
③財産目録・貸借対照表の作成
解散日における「財産目録」および「貸借対照表」を作成します。
これらは、会社法上作成を求められいる書類です。税務署に提出する書類ではありませんので、解散日後2月以内に税務官庁提出する「解散事業年度の確定申告書」には添付しません。
「財産目録」は、貸借対照表の資産、負債および正味財産の3つの部に区分した内訳明細です(会社法施行規則160条3項)。
記載内容は、処分価格を付すことが困難な場合を除いて、解散日における処分価格(清算価格)を付したものを記載することになっています。(会社法施行規則160条2項)
[詳細記事]財産目録の記載例
「貸借対照表」も処分価格を付したものを作成する点は、「財産目録」の作成と同様です。
[詳細記事]貸借対照表の記載例
④債権者に対する公告及び催告を行う
清算合同会社は、解散日後遅滞なく、2ヶ月を下回らない期間期間で、会社に対する債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけないことになっています。
さらに、債権者が誰であるかなどが分かっている者には、各別に催告しなければいけません。(会社法660条1項)
⑤「解散事業年度の確定申告書」の提出
解散日後2月以内に、税務官庁へ「解散事業年度の確定申告書」を提出し、申告税額を納付しなければいけません。
会社が事業年度の途中で解散した場合には、その事業年度の開始の日から解散の日までを1事業年度とみなします。(法人税法14条1項1号)
⑥債権取立・債務弁済・財産換価
売掛金等がある場合には、回収作業を行います。
買掛金や未払金、借入金等がある場合には、支払を行います。
車などの動産、土地・建物などの不動産、工具・器具・備品などの固定資産は、全て売却して現金化する作業を行います。
有価証券がある場合も、売却して現金化します。
ともかく、回収すべきものは回収して現金化し、支払わなければいけないものは支払を済ませ、他の資産も全て現金化します。
⑦「清算事業年度の確定申告書」の提出
解散の日の翌日から、定款等で定める事業年度終了の日までの期間を、清算中の事業年度として、事業年度終了の日後2月以内に「清算事業年度の確定申告書」を提出し、申告税額を納付を行います。
その後は、「定款等で定める期間が清算中の事業年度」となり、毎期の事業年度終了の日後2月以内に「清算事業年度の確定申告書」を提出し、申告税額を納付を行います。
<注釈>
この事業年度の区分の仕方は、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、協同組合並びに破産手続きの開始決定による解散の場合に用いられる清算事業年度の区切り方です。
この点、株式会社の場合と考え方が異なるので、注意が必要です。
⑧残余財産の確定及び分配
債務の弁済が終了し、会社の残余財産が確定したら、社員に分配する事が出来る様になります。(会社法664条)
分配割合は、原則として各社員の出資の価格に応じて分配します。
社員が複数で、出資の価格割合によらない分配を行うときは、寄付金課税の問題が生ずる可能性があるので、注意が必要です。
⑨「残余財産確定事業年度の確定申告書」の提出
残余財産が確定した日の翌日から1月以内に、「残余財産確定事業年度の確定申告書」を提出し、申告税額を納付を行います。
⑩清算結了の登記
清算事務が終了したら、清算に係る計算をして、その社員の承認の日から2週間以内(計算書の日付から2週間以内)に、清算結了の登記を行います。
この登記が完了すると、法的に法人格が消滅します。
[詳細記事]合同会社の「清算結了登記」に必要な書類と登記申請書の作り方
⑪「清算結了届」の提出
清算結了登記が終わったら遅滞なく、税務署・都道府県税事務所・市区町村に、「清算結了届」を提出します。
この届出を行うことで、会社が消滅したことを各官庁に通知することになります。
届出書の正式名称は、「異動届出書」です。
税務署への提出分の用紙は、国税庁のサイト 異動事項に関する届出 からPDF版の「異動届出書」を入手することができます。
都道府県および市区町村の用紙についても、各自治体のページからダウンロードで入手できます。
帳簿書類の保存期間は10年
清算人は、清算結了の登記がされた日から10年間、清算合同会社の帳簿とその事業、および清算に関する重要な書類を保存しておかなければいけないことになっています。(会社法672条1項)
社員の責任の消滅時効は5年
合同会社の社員の責任は、解散の登記をした後5年を経過した時に消滅します。(会社法673条1項)




